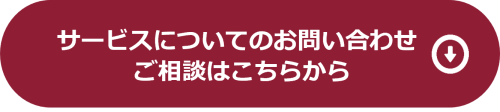ハラスメントは、社員の心身の健康や業務の効率に深刻な影響を与えるだけでなく、企業の信頼やブランドイメージにも損害を生むリスクがあります。職場でのハラスメントを防止し、対処するためには、社員一人ひとりが正しい知識と意識を持ち、お互いを尊重しながら適切なコミュニケーションを行うことが重要です。
研修では、ハラスメントの定義や種類、法的な責任や対策などを分かりやすく解説し、実践的なケーススタディやロールプレイを通して社員の理解とスキルを高め、ハラスメントを起こさない職場を目指していきます。
こんなお悩みはありませんか?

ハラスメントを恐れるあまり、管理職がメンバーの指導に腰が引けている…

ハラスメントにならない、効果的な部下指導のためのコミュニケーション法をお伝えします!
「ハラスメント」になる場合、ならない場合について知り、正しいコミュニケーションとハラスメントの線引きをすることが大切です。
声のかけ方、電話やメールなど、部下指導のコミュニケーションに対応したロールプレイングを実践して、当事者の気持ちを理解しましょう。

ハラスメントにならない効果的な関わり方やフィードバックスキルにばらつきがある。

職場でハラスメントを起こさないよう、組織が一丸となって体制、対策を取るきっかけを作ります。
組織として適切な指導や規律の維持がなされなければ、中長期的には大きな問題に発展してしまいかねません。
だからこそ、ハラスメントを防止すると共に、上司や管理職が萎縮しないようにハラスメントに関するきちんとした知識を身に着け、ハラスメントの基準や事例等に関する教育を実施していくことが重要です。
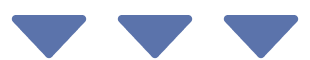
このような課題・ニーズにお応えします
- ハラスメント事案がコンプライアンス管理上、リスクであることを認識統一できていない。ハラスメントに対する認識に個人差があり、水面下で危険な状態かもしれない。
- 正しいコミュニケーションとハラスメントの線引きができていない。日常の挨拶、声のかけ方、電話やメールなど、あらゆるタイプのコミュニケーションに緊張感が漂う。
- ハラスメントにならない効果的なフィードバックスキルに、ばらつきがある。部下への指導や指示の際に、上司が遠慮したり、逆に威圧的になっていることに気づけていない。
ハラスメント研修が重要な理由
企業にとって、ハラスメント研修の実施がなぜ重要となるのでしょうか? ここでは、その理由を大きく2つお伝えします。
パワハラ防止対策における事業主の措置が義務付けられたため
2020年より労働施策総合推進法が改正され、パワハラ防止対策における事業主の措置が義務付けられました。これにより、企業にとって、ハラスメント研修の実施が今まで以上に重要となっています。
改正されたパワハラ防止法では、違反時の罰則は定められていませんが、必要な措置を行なわなかった場合、公的機関による助言・指導・勧告が行なわれます。万が一、措置を怠って訴訟になったり、ハラスメントの問題が報道されたりした場合、法的な処罰以上に、イメージ悪化等による損害が大きくなる可能性は否めません。
したがって、ハラスメント研修実施を含む職場での相談窓口の整備などをきちんと対応しておくことが重要になります。
ハラスメントは被害者だけでなく、組織全体にも悪影響を及ぼしかねないため
ハラスメント研修が重要な理由の2点目は、ハラスメントが被害者だけでなく、組織全体にも悪影響を及ぼすからです。ハラスメントを受けた社員は、仕事へのモチベーションやパフォーマンスが低下し、退職や休職にもつながりかねません。これは、組織の生産性や人材育成に大きな損失となってしまいます。
ハラスメント研修を受けることで、社員の意識や価値観を共有し、風通しの良い職場環境を作ることができます。これは、組織の生産性向上の上でも大切なことです。
職場で起こりやすいハラスメントの種類
実際に職場ではどのようなハラスメントが起こっているのでしょうか? ここでは、職場で起こりうるハラスメントを3つのパターン別に解説します。
仕事に関するハラスメント
仕事に関するハラスメントには、主に以下の3つの種類があります。
- パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメント、いわゆるパワハラは、職場内の地位の優位性を利用して精神的・肉体的苦痛を与えるハラスメントです。一般的に、上司の言動が「パワハラだ」とされますが、パワハラの対象は上司から部下への言動だけとは限りません。
例えば、正社員から非正規社員に対して、案件の依頼元から依頼者に対して、ときにはベテラン部下から新任の上司に対してなど、そこに「地位の優位性」があれば、パワハラとなりえます。
- モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメントとは舌打ちや噂話、悪口などの相手を傷つける言動を行なうハラスメントです。モラハラは、パワハラほど目立たない行為なだけに、継続的にストレスを受け精神的にダメージを受ける人も少なくなくありません。
また、行為があったその場で注意・指摘をしないと防ぐことも難しいため、いつの間にかメンタルヘルス等に追い込まれるリスクもあります。
- リストラハラスメント
リストラハラスメントとは、社内上層部がリストラ候補者に対して配置転換や雑務の押しつけを行ない、退職するよう仕向けるハラスメントです。権限等を背景にするという意味では、パワハラの一種ともいえます。
日本の労働環境では、企業が社員を解雇することが非常に難しくなっています。社員の就業環境が守られていること自体は素晴らしいのですが、結果としてリストラハラスメントのように陰湿な形で、自主退職するように仕向ける事象が発生しているわけです。
性差に関するハラスメント
性差に関するハラスメントは、セクハラを筆頭に大きく以下の4つがあります。
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメント、いわゆるセクハラは性的な言動を通して相手に苦痛を与えるハラスメントです。性的な要求を拒むと、その後に社内で不遇な処罰を受けるケースも発生しています。
セクハラは、男性から女性に対して行われるケースが大半です。他にも、上司から部下、正規社員から派遣社員やパート社員に対してなど、パワハラと同様に優越的な地位を利用して行われるケースも非常に多くなっています。
- ジェンダーハラスメント
ジェンダーハラスメントは「男らしさ」や「女らしさ」といった偏った価値基準で、相手に、立ち振る舞いや言葉遣い指摘したり、業務を無理やり押し付けたりするハラスメントです。
たとえば、「来客者には女性社員がお茶を出すべき」「男性なら文句を言わずに残業すべき」などはジェンダーハラスメントといえるでしょう。
- マタニティハラスメント(マタハラ)
マタニティハラスメントとは、妊娠中や産前産後の女性に対して、難しい業務や育休を取得させないなどの不当に扱うハラスメントです。女性の社会進出が進み、出産後も働き続ける人が増えた現在では、極端なマタハラは減少しているとは言えるでしょう。
しかし、産休や育休の制度はあるのに、実際に使いづらい雰囲気があるなどのケースは、マタニティハラスメントの一種ですので注意が必要です。
- パタニティハラスメント(パタハラ)
パタニティハラスメントとは、男性の子育て支援が推奨される中で、男性の育休に際して取得を妨げるような言動をしたり、取得後に不利な配属や異動をしたりすることをいいます。SNS等で大きく炎上したり、訴えられたりするケースも増えています。
近年は育休に関する世間の認識も変わっており、注意が必要なハラスメントの一つです。
その他のハラスメント
その他の種類のハラスメントは主に3つあります。
- アルコールハラスメント
アルコールハラスメントとは、飲み会などで飲酒や一気飲みを強要するハラスメントです。一昔前の時代はある程度”お酒の付き合い”として容認されていた側面もあるため、本人の自覚なしでアルハラを行なってしまう可能性もあります。
パワハラ・セクハラの大半はお酒が入る場で起きているという傾向もあり、特に職場での飲み会等は、注意すべき場といえるでしょう。
- スメルハラスメント
スメルハラスメントとは、臭いが原因で周囲に不快な思いを与えるハラスメントです。体臭などは本人が気付いていないケースも珍しくありません。
本人には悪気が無いだけに、直接指摘するなどが難しい問題ですが、最近ではこうしたことも職場におけるハラスメントとしてトラブルになるケースがあります。
- レイシャスハラスメント
レイシャルハラスメントとは人種、国籍、地域などの生まれつきの括りで、嫌がらせや不当な差別をするハラスメントです。
グローバル化に伴って外国人労働者の方が増えていたりしていることもあり、今後はいっそう注意が必要なハラスメントと言えます。
ハラスメント研修の目的
ハラスメント研修を行う目的を大きく3つ解説します。
職場の環境・風土の改善
ハラスメントは、被害者だけでなく周囲の人や組織全体にも悪影響を及ぼします。ハラスメントによって職場の雰囲気が悪化し、コミュニケーションが阻害される可能性もあるでしょう。
ハラスメント研修によって、社員はハラスメントを防止する方法や解決する方法を身につけ、お互いに尊重し合い、多様性を認め合える職場環境・風土の改善につながります。
従業員の意識向上
ハラスメント研修では、ハラスメントについて学ぶだけではなく、社員1人ひとりの意識や価値観の違いに気付き、相互理解を深めることも目指していきます。
ハラスメントに対する意識が向上することで、社員は適切な行動を取れるようになります。
社会的リスクの回避
ハラスメントは、個人や組織の社会的な信用失墜を引き起こす可能性があります。ハラスメントを受けた社員が会社を訴えたり、メディアで暴露したりすると、顧客からの信用や評価を失い、採用や離職率にも影響を与えるでしょう。
ハラスメント研修で、社員がハラスメントの社会的な影響やリスクについて学び、ハラスメントを未然に防ぐことによって、社会的リスクの回避にもつながります。
ハラスメント研修の特徴
ジェイックのハラスメント研修の特徴を3つお伝えします
ハラスメントの定義を基礎から学び、組織としての統一見解を学ぶ
ハラスメントとは、性別や年齢、人種や国籍などの特定の属性に基づいて、相手に不利益や不快感を与える言動や態度のことです。ハラスメントは、法律や社会規範に反するだけでなく、組織の生産性や信頼性を低下させるリスクがあります。
ハラスメント研修では、ハラスメントの種類や事例、判断基準や対処方法などを基礎から学びます。また、組織内でハラスメントに対する統一の見解や方針を共有し、予防や防止の意識を高めます。

ケーススタディやロールプレイングを通して、当事者の気持ちを理解する
ハラスメントは、当事者だけでなく、周囲の人や組織全体にも影響を及ぼします。ハラスメント研修では、実際に起こったハラスメントのケーススタディやロールプレイングを行います。
これにより、ハラスメントを受けた人や加害者、目撃者などの立場に立って、それぞれの気持ちや思考を理解します。また、ハラスメントが起こった場合の適切な対応や報告などの方法も学びます。

ハラスメントに対して組織が一丸となって体制、対策を取るきっかけを作る
ハラスメントは、個人の問題ではなく、組織の問題です。ハラスメント研修では、組織としてハラスメントに対する姿勢や責任を明確にします。
また、ハラスメントが発生しないようにするための体制や対策を検討し、実行するきっかけを作ります。例えば、ハラスメント防止委員会の設置や運営、ハラスメント相談窓口の開設や活用、ハラスメント教育の定期的な実施などです。

カリキュラム例
- 所要時間:約6時間
ハラスメントの基礎知識
- ハラスメントとは?
- ハラスメントリスクとは?
- ハラスメントリスクに対応する意義
セクシャルハラスメント
- 「セクハラ」になる場合、ならない場合
- セクシャルハラスメント問題の概観
パワーハラスメント
- 「パワハラ」になる場合、ならない場合
- パワーハラスメント問題の概観
ハラスメントのない組織づくりのために
- 経営理念から、あるべき姿を考える
- ハラスメントを防止するために
- 自らの傾向を知る
ハラスメントを起こさない部下指導を考える
- 効果的な部下指導のためのコミュニケーション法
- ハラスメント発生時の対応ポイント
実践演習:ロールプレイング
まとめ(課題説明、質疑応答)
| 開催地 | 講師派遣型なので全国対応可 |
|---|---|
| 期間 | 1日間 |
| 総研修期間 | 約6時間 |
受講者の声

ハラスメントは誰にでも起こりえる問題だと再認識できました
今日まで、ハラスメントに対しての正しい知識を持っている従業員は少なかったと思います。基礎や定義を教えていただくことで、いつ誰にでも起こりうる問題だと再認識できました。

日頃からの活動、関わり方の重要性を学びました
日頃から営業所内での関係・環境づくりを行っていくことで、問題になる前に相談しやすい風通しのよい職場にしていく事や、部下への指導方法などを改めて見直させていただきました。

自分だけでなく、メンバーや組織全体に浸透させる必要性を痛感しました
今回の研修を自身がしっかりと理解し、メンバーにも理解してもらう必要があると思います。そして、モラルの判断軸を組織で合わせていく必要があると感じました。
講師紹介
ハラスメント研修でよくある質問
ハラスメント研修の受講者はどのように選定すればいいですか?
ハラスメント研修では、基本的に全従業員を対象にします。受講者には非正規社員やパート・アルバイトの人も含まれます。ただし、内容によっては、管理監督者だけを対象に実施するケースもあります。
管理監督者は、部署内のハラスメントを防止することが重要な役割のひとつであるため、特に意識して深く学んでおく必要があります。
ハラスメント研修を実施する頻度はどのくらいが良いでしょうか?
ハラスメント研修を実施する頻度は、年に1回以上が理想です。ハラスメントは常に変化する社会的な問題であり、法律や社会通念も変わっていきます。そのため、定期的に最新の情報や事例を知っておくことが重要です。
また、直接の目的ではありませんが、ハラスメント研修を通じて社員全体の意識や価値観を共有し、ハラスメントを起こさない職場環境についてディスカッションすることも効果的です。
あわせて、研修だけではなく、日常的なコミュニケーションやフィードバック、相談体制なども整備するようにしましょう。
自社でハラスメント研修を実施する時のポイントは何でしょうか?
自社でハラスメント研修を実施する上でのポイントは大きく2つあります。 1つ目は、定期的に繰り返し行うということです。ハラスメントへの意識は一回の研修で変わるものではなく、社員が理解し行動に定着させるまでに時間を要します。したがって、一度実施したから大丈夫と考えるのではなく、定期的に繰り返し行うことで、ハラスメントに対する意識を少しずつ変えていくことが望ましいです。
2つ目は、自社の社風、組織カルチャーを盛り込んだ内容にすることです。なぜなら、ハラスメントが起きる背景には、企業風土など組織や職場ならではの要因が背景にあることが多いからです。また、自社の企業風土を踏まえたプログラムにすることで、参加者は研修を自分事化しやすくなり、研修の効果が上がります。
ジェイックが提供するハラスメント研修では、企業様ごとの社風やカルチャーに合わせたカリキュラムをご提案しています。